

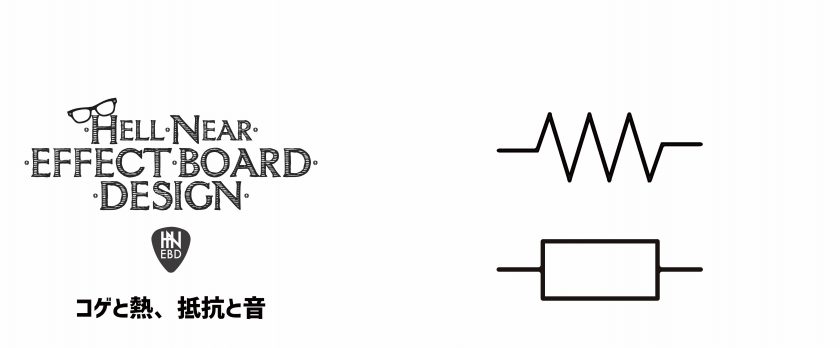
札幌のエフェクターボード製作屋、ヘルニアエフェクトボードデザイン根尾です。

私は鉄のフライパンが好きです。と言ってもあるのは一枚なのでさほど好きでもないように思えますが、手入れすれば早々ダメにはならない、多少手のかかるモノでも永く使えるモノが好きなので長いこと使っています。なんでもだいたい美味しくなりますしね。焼きそばと炒飯、卵系はとくに。
キャストアイアンの小さいスキレット(6 1/2 inch)も使っていますが、キャンプで使うのは主にこっちで。元々鉄のフライパンってキャンプ道具を調べてた中で知ったわけですが、実際持っていくには重過ぎると思うんですよね。小型サイズのスキレットでも充分重い。そこまで食べるを重視しない時は持って行かないこともしばしば。
で、鉄のフライパンは亀の子たわし、たまにステンレスたわしで洗うわけですが、だんだん黒くなっていくんですよね。
黒くなるのは 酸化被膜、油膜なんてワードが調べるとでてきますが、ヘリに残る黒い何か、表面のスリットが黒く埋まってしまってたり、くっつくようになってきたり、どうも変だぞ、となった時、私は一度リセットするような感覚でステンレスたわしで落としています。
しぶとい黒いのはコゲだと思っていますが、これらはどうも硬いんですよね。
なんの話だ、となりそうなのでアレですが、日常生活と楽器関連は諸々共通しているなー、とお皿洗いしながらボケッと思ったことを。
と思う、というお話。
鉄のフライパンって料理に使う面は完全に冷め切らないうちにお湯と亀の子たわしでこすればすぐ落ちます。裏もさーっとたわしでこすって流したら水分拭き取って少し火にかける。水分飛ばしたらひっかけて終了、フライパン自身、持ち手のエンドがひっかかる形状をしてくれているのですごく楽なんですよね。私にとっては。
しばらく使っているとフライパンの表面も裏面も黒くなってくるもので。
最初はこういうもんなんだろう、と勝手に思っていましたがよくよく考えてみるとしぶとく残っているのはコゲなんじゃないかと。
こうなってくると最初の頃よりもなんとなく熱の入りが遅い気もする、コゲが抵抗になって熱源との間を邪魔している気がしてきたんですよね。
ここでステンレスたわしの出番なわけですが、新しいうちはたわしパワーが強く比較的楽にフライパンが買った頃の姿、色味に戻っていくわけです。
一点注意が必要なのは食器洗い時にゴム手袋をはく場合、ゴム手袋がけっこう黒くなります。ステンレスたわしの後に亀の子たわしでもこすって流さないと水分拭き取り時、真っ黒になったり鉄臭くなるのでたわしを変えた二段階がおすすめです。
と、ここまでは完全に私のフライパンライフのお話でしたが、これはですね、ギターやベース、シールドのプラグにも同じことが言えると思うんです。
もっとも近いところが弦とフレットです。
弦は錆びてきたら交換、そういうモノですよね。ではフレットはどうでしょうか。交換のご依頼もあるフレットですが普段のケアで大きく変えられる部分でもあります。
夏を越えたフレットはステンレス製を除き、だいたいくすんでいると思います。
ここを磨いてあげることによって、弾き心地、音の立ち上がり、レスポンスもグッと変わるわけですね。くすみは酸化、なんらかの膜がある状態、ヴィブラートをかけた時になんかぐすぐすひっかかる、抵抗になっている状態であると思います。
酸化した状態のフレットはこんな感じですね。これを磨いてピカピカにします。

金属ゆえ、ご使用状況、保管環境によって時間差はあっても必ず起こることなので、うちは弦交換はフレット磨きがセットです。
チョーキングもヴィブラートもスルスルスムーズ、嫌なひっかかりが消えるというのは弾いていて楽しい、楽しくないにも関わってくるところですのでフレットのケアは激しく大事だと思います。
余談ですが弦のサビは硬いのでフレットを炒める… あ、痛めるだ、フレットが減りやすい状態になってしまいますので、定期的な弦交換は楽器自体の寿命を伸ばすものだと思っております。
あまりに湿度の高いところに長年あった楽器はフレットにサビがでてしまっていることもあります。こうなるとガキッとひっかかりがでるのでサビは硬い、がわかりやすく、サビを落とすのは大変です。
シールドのプラグ部分も普段から定期的に使っているものは起きにくいですが、使っていない期間が長いとくすみが出てきます。
この酸化膜もやはり抵抗、音を伝達する部分ですので、くすんでツヤがない状態で楽器に入力しても本領発揮の音とは言えず、厳密に言うとですが楽器側、ジャック部分の劣化にもつながりますので、プラグのくすみがある場合は無水エタノールで拭いてケアすることも大事だと思います。
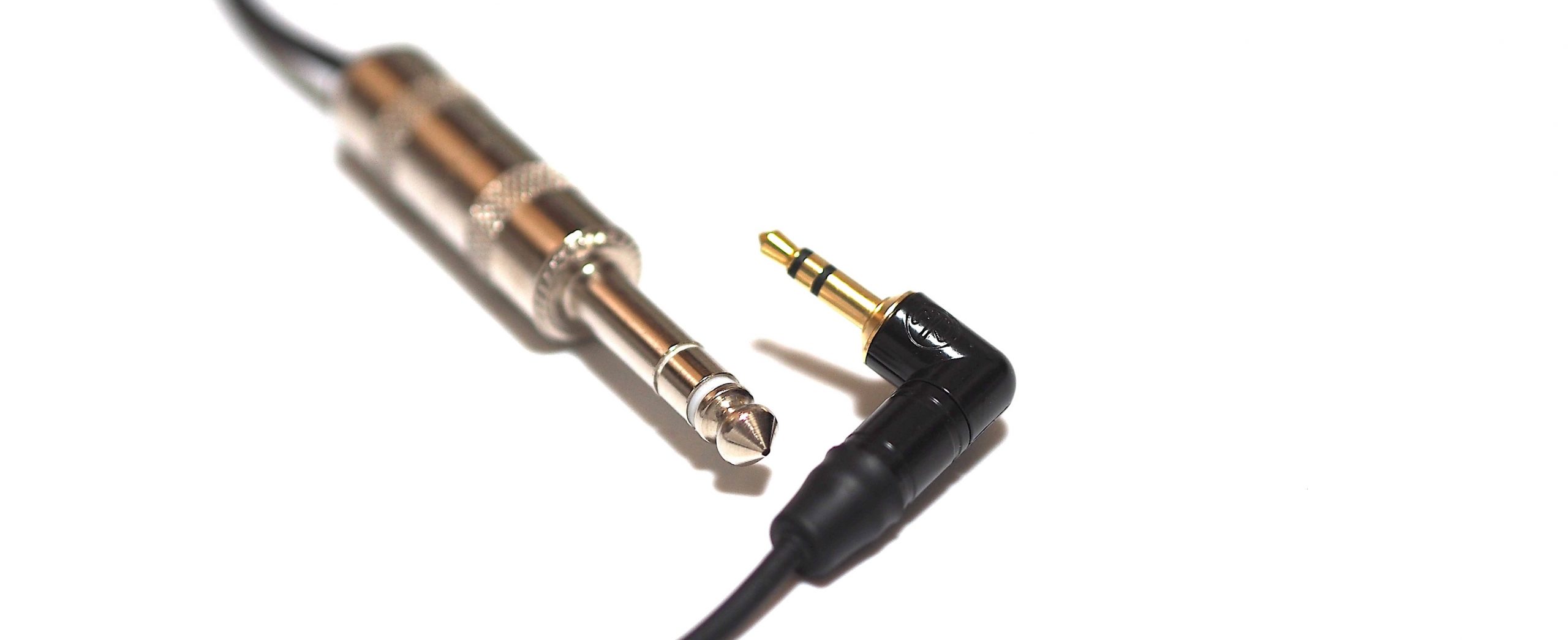
あとはハンダですね。モッリモリなイモハンダもそこは抵抗、適度なハンダ量よりもなんらかの抵抗になっていると思います。ハンダの量でも音が変わりますので、やはりそれは抵抗であると。
さらに言うと熱を与え過ぎて曇ったハンダよりも適度な時間で仕上げるキラっと光った状態のハンダの方が音も良いと考えています。
大半がフライパンの話になりましたが、道具の手入れ、楽器も手入れ、さらには調整と、長く良い状態で使うには必要なものかと思います。
定期的、という言葉を多めに使いましたが、私が楽器店に入った時、楽器の最大のメンテナンスは毎日少しでも定期的に弾くこと、という教えがありました。状態の確認にもなりますしね。
5分でも10分でも弾く、音の振動が定期的にあれば私は楽器である、と楽器サイドも認識してくれる、長年弾かれていない楽器の狂い方を見ると楽器的に私は木であった、と元の姿に戻ろうとしてるんじゃないか、と私は思うんですよね。
フライパンもしばらく使わないと状態がわかりやすく悪くなるもので、日々使う、定期的に使っているといい感じが続き、なんか変だなっていう変化にも気づきやすくなる、楽器と鉄のフライパンはやはり一緒だな、というお話しでした。
今回は画像が少ないので最近作ったシールドを載せてみます。

★ 2022年に製作させていただきましたギタリスト高橋 克 様のエフェクターボードを 「こちら祇園二丁目濱田製作所 様」にてご紹介いただきました。ありがとうございます。HELL NEAR EFFECT BOARD DESIGN 製のエフェクターボードの音がご本人様の演奏で聴けます。
★ 過去製作は Instagram に載せておりますのでチェックしていただけると嬉しいです。
→Instagramはこちら
『全都道府県に製作実績を』を今後の目標にしておりますので、日本全国よりご相談、製作のご依頼、心よりお待ちしております。フォローしていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。